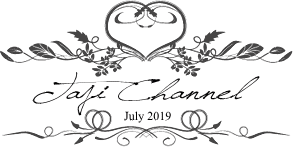古い因習からの独立を謳う前衛的集団「クリスチャニア・ボヘーム」で、ムンク自身はイエーガーを尊敬しながらも、この集団に属する人々を外から批判含みに眺める存在でもあった。意志が強く、感受性豊かで容貌にも恵まれた芸術家ムンクは、多くの同時代の文化人や芸術家と出会い、当然のようにさまざまな愛憎劇に巻き込まれていった。
社交界の花であった人妻との不倫に悩み、奔放な時代のミューズに夢中になり同志の友と競い合った。パリ留学の合い間に訪れたオースゴールストラン(ノルウェー南部のリゾート地)では、師であるクローグの妻に誘惑され、その愛人ヤッペ・ニルセンも加わった複雑な愛のもつれを体験する。
家族を次々と失った過去から生じた家庭を持つことへの恐れと、これら苦悩に満ちた女性問題の経験は、彼の作品に色濃く映し出されている。

夫人でありながら恋を奔放に愉しむ、
貪欲な「女」という魔物の二重性。
ムンクの初恋の相手がモデルといわれている。
魅惑的な視線を投げる黒服の女の表の顔と、
影法師に隠された破滅的な裏の顔が、
黒の二重奏となり迫りくる。
反射した光の白さがなまめかしい。

女は死に等しい恍惚の表情を浮かべ、
それを血のように赤い光輪が支える。
性の交わりで男は精気を吸い尽くされる。
忘我の悦びとともに訪れる死の影。
抗いがたい愛憎のさなかにも、
ムンクは死を垣間見る。
別名「受胎」とも呼ばれる作品。
櫛の歯が欠けるように失われてゆく家族、性愛の渦中に垣間見える死の影。ムンクの精神が荒み、鋭く脆くなるほどに、それを鏡のように曝(さら)け出す絵は評価を高めていく。経済的に安定したムンクは、オースゴールストランに仲間とともにアトリエを購入し、しばしばそこに滞在しながら制作活動を行った。
結婚生活に耐えきれず虚弱な弟があっけなく死を迎え、自らも同じように体が弱く生の不安を感じていた彼にとって結婚は否定的なものでしかなかったが、そんな折に恋人トゥーラ・ラールセンとの間に起こった1902年の銃暴発事件は、決定的なダメージになった。
その後、彼女は夢中に追い求めていたムンクを捨てて、彼の同僚だった男とあてつけのように結婚する。ムンクは以後、友人ニルセンに恨みがましく痛む指を見せては、彼女への不満を漏らしていたという。魅惑的な女たちに振り回されてきた彼にとって、女性は抗いがたく、受け入れがたい存在であり続けた。

「罪」1902
衝撃的な ”狂気” を内含する3色刷り。
これに出会った時は、
思わず足が止まる迫力の視線であった。
モデルは結婚を拒むムンクの指を
銃の暴発事故で吹き飛ばした恋人、
トゥーラ・ラールセン。
強迫観念に苛まれ、アルコールに依存し、ついいにムンクは自主的にコペンハーゲンの精神病院に入ることを決意する。電気ショックの治療を彼が受ける一方、翌年の1909年、ニルセンらの尽力で油彩100点と版画200点の「大ムンク展」が母国で開催され、母国ノルウェーにおける評価もようやく確たるものになった。そして、治療の一環として書いた詩文集は彼を女性たちとの確執から解放し、半年余りの療養を経てノルウェーに戻る。
心の安定を取り戻すのに伴い、キャンパスにはフォービズムを思わせる、生命感を湛えた明るい色が増えていった。社会生活を送ることの出来る心の安定と引き換えに、それまで心にこびりついていた不安や、病的な叫びをあげていた感受性が、少しずつ和らぎを見せてゆく。

「太陽」1909-1911
後期、内に巣食う病や悩みを乗り越えようとするかのように、
ヴィヴィッドで強い光の作品が増えていく。
闘病を経て、正式にオスロ大学に依頼されたこの作品では、
北欧の命の源となる、太陽の輝きを描いている。
ようやく心の安定を得て、彼はノルウェーにアトリエを構え、理解ある両手で数えられるほどの限られた友人たちと交流して過ごすようになった。彼は自身の芸術の原点が、故郷の景色や個人的体験に帰依するものだと理解していた。ゆえに、かつて自らを蝕んだ精神を否定し取り除くのではなく、凍てつく雪原とフィヨルドの国で冷やし鈍らせ、共存する道を選んだのであろう。
医師に勧められ描き始めた友人たちの肖像画は、描き上がった後も手放すことなく、大切に彼のアトリエに集められていたという。

「ヤッペ・ニルセンの肖像」1909
かつて自由恋愛のライバルだったニルセンは、
やがて身近で大切な理解者となり、
満身創痍の魂に寄り沿い力付ける生涯の友になった。
顎を引きすっくと立つ長身の男からは、
安定感と信頼に足る人柄が伝わって来る。
穏やかな緑や落ち着いた服の色には、
相互的なリスペクトが感じられる。
ほぼ等身大に描かれたこの絵はアトリエで、
本人がそばにいない時でも、
ムンクの心を支えていたいに違いない。
19世紀末に向かうノルウェーでは、漁業・海運・製紙などが産業革命により目覚ましい発展をとげ、民主化や自由主義の機運が整っていた。長く支配されていたデンマークからスウェーデンに割譲されていたノルウェーは、1905年にようやく、デンマークの王子を迎え立憲君主制としての独立を手にした。
この頃のムンクは、秀逸な肖像画で生計を安定させるようになり、力みなぎる労働者たちの姿を残している。

「家路につく労働者たち」1913-1914
この時期取り組んでいた労働者シリーズのひとつ。
葛藤や心の闇を描いていたかつてとは異なり、
働く人々をモチーフとし力強い線を残している。
退屈にも見える繰り返しの中で着実に生きる姿。
手足を使った作業は目の前の事に集中させ、
よい意味での鈍感力=心の安定と結びつく。
鋭敏過ぎる魂と引き換えに成功した彼には
けして加わることのできない労働者の生き様に向け、
表に出すことのできない憧れとも、諦念ともとれる
やや屈折した想いがそこにあるように思える。
晩年はオスロ郊外の広い邸宅で、目の病や成功を妬む者からの嫌がらせに悩まされる一方、作品が初めに評価されたドイツ、ようやく認めてくれた母国ノルウェー、最も愛し愛されたフランスから、それぞれ勲章を授かるという栄誉にも恵まれた。
しかしナチスドイツの台頭とともに、 ”退廃芸術” の烙印を押された彼の作品はドイツの美術館から外されてしまう。ユダヤ迫害は大切な彼のパトロンを奪い、友人や理解者の多いドイツと愛するフランスが引き裂かれたことは、老いた彼の心を悲しませた。ナチスに作品を没収されるのを恐れたムンクは、アトリエに引きこもり制作を続けた。

「時計とベッドの間の自画像」1940-1942
明るく陽気な色彩に囲まれながら、
自省と孤独感が漂う姿。
人気のあった肖像画制作に
いかんなく発揮された鋭い観察眼は、
己にも容赦なく向けられている。
人生をかけた自身の芸術を奪われる
脅威にさらされていた、晩年の作。
そんなある冬の12月、80歳の誕生日を祝ったすぐ後のこと、自宅近くで起きたレジスタンス活動によって彼の家の窓ガラスが吹き飛ばされてしまう。家の中へと流れ込む冷気で気管支炎を起こしたムンクは、ひと月後ついに帰らぬ人となった。
彼が怖れたナチス・ドイツが降伏し、世界大戦が終焉を迎えたのは、その翌年の1945年だった。
多くの画家・作家らが自らの感受性に殺されて世を去る中で、ムンクは愛憎と時代の激動を辛くもくぐり抜け、80年という歳月を生き延びた。
たった一人の心の中に生まれた戦慄や不安を、全ての人に湧き起こる普遍性として描き出したムンク。そうして生まれた作品は、自らが苦しんだ遺伝的素因を畏れた彼が、唯一この世に遺してゆくことのできた子供たちなのかもしれない。
参考文献:アートギャラリー現代世界の美術・ムンク(集英社)
エドヴァール・ムンク(TASCHEN)
Edvard Munch(PARCO出版)
2