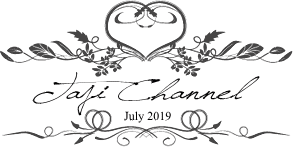「秋翳」1958(昭33)
やわらかな曇り空に
ほっくりと浮かぶ紅葉の山。
一本一本がそれぞれにこれでもかと、
冬を前に体を染め上げて競い合う。
上質な和菓子を思わせるその色合いには
豊かな秋の味わいがある。
日本画家としてその評価を確立した魁夷は、東宮御所や皇居宮殿、唐招提寺障壁画の大作をも依頼されるほどになる。その合間に北欧・京都・ドイツ・中国などを旅し、新たに出逢った自然の在り様に心動かされ、その画風に厚みを増していった。
彼の絵には、かつて彼自身が人生で感じた何らかの感情が含まれている。静かに自然を見つめたとき、そこには彼がどこかで経験した、心の風景が投影されるのである。人のあらわれない魁夷の風景を見て感じるほんの僅かな人為は、この感情が風景の中に隠れているからなのだ。心象の風景画・・・東山画伯の絵はそう称されている。

「行く秋」1990(平2)
枯葉、落葉ということばには、
一抹の淋しさがつきまとう。
だがここでは冬を目前に散り行く落葉樹の、
たっぷりとした深みと実りを暗示させる。
しきつめられた黄金の絨毯をかさかさと踏みしめるとき、
きっと私たちには足の裏に、
燦然と輝く力強い生命の昇華を感じ取るのだろう。
油絵のような艶と色彩の日本画もあれば、水墨画のように色彩を控えて崇高な自然を見せる作品もある。はじめ油絵を描いていた魁夷が日本画科で学んだのは、父親が画家を目指す条件としてそれを提示したからであった。
油絵の素養、ドイツへの留学、同志の仲間のさまざまな画風・・・それらが彼の作品に影響を与えたからこそ、独自の作風が出来あがっていったのだろう。底に流れているものは一貫していても、彼の筆は非常に多彩で饒舌である。

「照紅葉」1968(昭43)
輝く黄金色の黄葉の、合間に覗く木々の灰紫。
反対色のコントラストと画面分割を用いた、
艶やかな秋の錦。
その画面に独特のリズムを生んでいる理由のひとつは、ドイツ留学中の音楽の素養かもしれない。モーツァルトを愛聴していたという魁夷。「弦楽器の合奏の中を、ピアノの静かな旋律が通り過ぎる」・・・『緑響く』に寄せた彼の言葉である。

「雪降る」1961(昭36)
降りつづける雪の中に
画家は自分の姿を投影する。
木の塊と手前の川との距離は、
殻に閉じこもった自分と外の世界との距離だろうか。
単純化されたモチーフは、
心象を際立たせる。
彼にとって絵を描くことは、『祈り』であるという。運命によって、 日本画家に “され” 、風景画を “描かされ” ていると彼は言う。自然や人間の営みに対する敬虔な祈りが、彼に絵筆を運ばせる・・・描くことは、魁夷にとって自身のいのちの昇華でもあるのだろう。
人生という長い長い旅路の中で、彼は出会った風景に自分の心を見つけ、そして祈った。その絵は決して対象を超えることなく、等身大に描かれているはずなのだが、そこにひそめられた心がどこからともなく涌き出て、私たちの心に共鳴する。

「白い朝」1980(昭55)
小さな身体のともしびを逃がさぬよう、
凍えるような朝にじっと枝にとまる一羽の鳩。
ささやかな命が、必死で生きようとしている。
何を思うでもなく、ただ。
半世紀もの間、大自然の囁きに、そして自らに与えられたいのちに、訥々と祈り続けた日本画壇の巨匠は1999年5月、この世でいちばん長い旅路を終えた。
しかしその作品は今までも、これからも、永遠に伝えられていくことだろう。

「山峡朝霧」1983(昭58)
立ち上る冷たい霧に
身を湿らせ立ち尽くす斜面の木々。
水墨画のように色彩を抑えて描かれた夜明けの風景には
敬虔な生命の唱和が聴こえてくる。