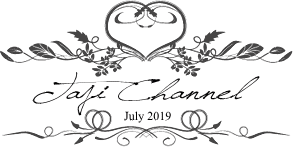まるで理解する必要でもあるかのように
Claude Monet(1840-1926)
皆が私の絵を論じたり理解したふりをするけれど、
ただ好きになってくれればそれでいいんだ。
To know more about MONET….
“Giverny 1926” by precious.

歩いてくるまでの時の移ろいの中でも、
景色はそよぎながら変わらず穏やかにたたずむ。
鮮やかなひなげしが両手をいっぱいに広げ、
妻のカミーユと息子のジャンを優しく包み込む。
ルノワール、セザンヌらと並ぶ、印象派の巨匠クロード・モネ。 現在、多くのファンを持つこの一派が、 世の中に認められるまでにどれほどの努力と時間を費やしたことだろう。 そしてどれほどの誹謗と中傷に耐えなければならなかったのだろう?
北フランスの雄大な自然を見つめながら育ち、画家を目指すために学校を中退したモネ。この頃の作品に影響を与えたのは、陽光のもとでなつかしい色合いの海景を描くウジューヌ・ブーダン、そしてつぶてとなって目に飛び込む光の風景を描くヨハン・バルキント・ヨンキントであった。
モネらしいのびやかにキャンバスに広がる風景と光を捉える一対の目は、この2人の素晴らしい師の手ほどきによって、さらなる次元へと開花していくのだった。

「サン・シメオン農場への道」1864
モネ24歳時の作品。
まだまだ暗い色彩だが、
中央の抜ける青、道に横たわる木洩れ日の鮮やかさには、
モネの「光をとらえる目」が確かに感じられる。
パリの画家たちにとってサロンは、確かに世に認められる発表の場にもなったが、一方では辛らつな批評家たちの一言で、現在素晴らしいと思われている作品が意味のない一枚に失墜するのも日常茶飯事であった。
画家として歩み始めた彼は、ルノワールやバジールといった同志と共に、大胆で光に満ちた作品を描きつづける。しかし比較的好意を持って迎えられていたサロンで初めて大絶賛を受けたのは、皮肉なことに室内の人物像である「緑衣の女」であった。
この成功によりしばらくは、サロンでの成功の大前提である「人物」を取り入れた作品が続くが、やはり彼のテーマは「外界の光」へと回帰していく。

その一部になるパリの往来。

印象派の言葉のもとになった作品。
色と色の隙間、形のない筆致は
当時嘲笑の的になり、
長い間陽の目をみることはなかった。
「緑衣の女」以来、成功とは縁遠く貧しい状況にあったモネは、友人や親類からの援助で生計を立てながら、それでも光に満ちた風景を描くことをやめようとはしなかった。
色はいっそう光の集合となり、徐々に人物の影は風景に同化してゆき、それは更に彼をサロンから遠のける原因となった。戸外で描くことはまだ一般的ではなかったのだ。

人の影、草の根元には、みじんの曇りも見られない。
まばゆいばかりの光と色彩に満ちた世界が
画家の生涯のテーマであった。
債権者に追われてモネとカミーユ、そして息子のジャンはさまざまな土地をわたり歩く。
やがて父の遺産と、少数ではあるが彼の支援者のおかげで、ひとときの中流階級の生活を手に入れる。その頃の穏やかな日々に包まれた小さな幸せは、あたたかな日差しの中に描かれる愛する家族の姿にも感じとれる。
ようやく手にした束の間の幸せののち、再び困窮はやって来る。そして苦労を共にしてきた愛妻カミーユが、2人の子供を残して32歳という若さで死の床につく。彼女のデスマスクを絵として残したことについては冷酷だという批評もあるが、周囲の反対にも関わらず共に手に手をとって歩んだ彼女のこの姿は、愛していたからこそ残さずにいられなかったものであろう。

「死の床のカミーユ」1879
モネは制作中にふと我に返り、
「私は何ということをしているのだ」と自分自身を責め、
描くことしか出来ない己を呪い哀しむ。
けれどこの絵の前に立った時、
涙が自然と溢れてきた。
つかず離れず優しい風のように顔を包む幾重もの線は、
精一杯の愛情で妻の顔を包み込むモネの両手。
胸元の花の紅はカミーユへの感謝を、
ひそやかに枕元を照らす柔らかい光は尊敬を、
象徴しているように感じられる。
わずかな幸せしか与えられなかった
最愛の妻の生涯を描くことで抱きしめ、慈しみ、
忘れ得ぬものに昇華させたのだ。
その筆致は限りなく優しく、悲しみに満ちている。
相変わらず酷評を浴びせられる印象派の画家のみならず、数少ない確かな目を持ったコレクターたちも、同様の扱いを受けていた。早くからその一人として「印象、日の出」の所有者でもあった、エルネスト・オシュデ。そのオシュデの未亡人アリスと6人の子供は、カミーユ亡き後の良きモネの理解者として、共に安息を求めて土地を渡り歩くことになる。

これぞ太陽のもと!
藁草のstraw-yellow、かすむ海の繊細な青。
輝ける色と光を余すところなく捉える、
奇蹟のようなモネの一対の眼。
これらの移動の中でモネは繰り返し同じ風景を描き、時間により、空気により変化する風景を、誠実に見つめ追い続けるようになる。「積みわら」「ポプラ」「ルーアン大聖堂」・・・これらの連作は長きにわたり冷遇されてきた、印象派としてのモネの成功へようやく導いた。
モネは既に50歳。
しかし長かった不遇の日々は、彼に不屈の精神と自分の作品への信念をより強くさせていた。

「ルーアン大聖堂」連作より1894
左:夜明けの扉口とアルバン塔
中央:扉口朝の日射し、青のハーモニー
右:扉口とアルバン塔、溢れる陽光、青と金のハーモニー
いくつものキャンバスを前に、
時間とともに移動しつつ描く連作から3点。
余計なことばは不要ですね。どうぞご鑑賞下さい!
アリスと結婚し、大家族になったモネの最後の土地・ジヴェルニーには、彼の理想とする庭園が徹底して作られていった。主な絵の対象は庭園と旅行先へと絞られていく。
モネはたくさんのキャンバスをアトリエに保存し、長い時間をかけて少しずつ少しずつ色を重ねた。無数の絵が満足行かずに、自らの手により焼却された。そして印象派としての成功を手にしたのちも、過去に酷評された絵を、アトリエにそっと慈しむように置いて手放さなかったという。

「モネ家の庭の小道、ジヴェルニー」1901-02
あらゆる花をここへ集めたかのような、
画面に広がる色彩のメッセージ。
絵を見つめるだけで、両手いっぱいに
花を抱いているような気持ちで満たされる。
肌には太陽の暖かさと、植物の湿度を感じて。

「Les Glycines(藤)」部分1901-02
満ち満ちた溜息とともに絵の前のソファで動けなくなった。
いくら眺めても飽きないその豊かに立ち昇る芳香。
居心地がよくてどれくらいその前にいただろうか、
名残惜しみながらマルモッタン美術館を後にした。

「ヴェネツィアのたそがれ」1908
目にうつる光と色彩を、的確にうつしとる彼の画法。
その意味で客観的な彼の作品中で、
この絵はひときわ感傷的でロマンティックで、
まるで夢の中の幻影のよう。
晩年旅行先にて目にしたこの風景に動かされた
彼の心が画面の揺らぎとなって、
私たちに伝わってくるからではなかろうか。
防寒着に身を包み、帽子を被り、冷たい風に身をきられながら黙々と絵筆を走らせるモネ。そしてある時は燦燦と輝く日の下で、まぶしい光を捉え続けるモネ。そんなひたむきにキャンバスに向かう姿が、彼の絵からは想像できる。
永遠に完成することがないかのように、キャンバスに塗り重ねられる色彩。長い長い信念の時を経て、晩年彼は完熟の作品を残すことが出来たのだ。

「睡蓮」1906年頃
青さに浮かぶ、ジヴェルニーの可憐な睡蓮たち。
絵を前に深呼吸すると、鼻のなかに広がるのは
池にたちのぼるあたたまった水蒸気と、
むせかえるようなハスの香り。
そのままいつまでも・・・。
参考文献:モネ(TASCHEN)